
更新日:2025/09/10
今年(2025年)の「重陽の節句」は 9月9日(火)。
五節句のひとつで「菊の節句」とも「栗の節句」とも言われます。
長寿と健康を願う日を、やさしく・おしゃれに楽しむヒントをまとめました。
菊を愛で、菊酒を飲み、邪気を祓いましょう!

重陽の節句はいつ?

9月9日。
菊と栗で邪気を祓いましょう!
この記事でわかること
- 重陽の節句の「由来・意味」を2分で理解
- 菊・登高・着せ綿などキーワードを解説
- 当日に“何をすればいいか”が一目でわかる実践リスト
- よくある質問(旧暦との関係、行事食、後の雛 ほか)
重陽の節句とは?
- 日付:9月9日(新暦)。
- 五節句(人日1/7、上巳3/3、端午5/5、七夕7/7、重陽9/9)のひとつ。
- 別名 「菊の節句」。菊は不老長寿の象徴で、長寿と無病息災を願う日。
- 陰陽思想では奇数=「陽」。“9”は最大の陽数で、その重なり(重なる陽)から重陽と呼びます。
- 旧暦では菊が最も美しい時季にあたり、現在も各地で観菊の催しが開かれます。
「重陽の節句」由来

中国の重陽節が起源。
中国では古くから奇数が縁起の良い陽の数字とされ、一番大きな数である「9」が重なる9月9日は「重九」「長陽」と呼ばれ、縁起の良い数字が重なることで逆に不吉な日とされ、もともとは厄払いする日とされています。
中国の古い風習では、重陽の節句には、茱萸(しゅゆ/ぐみ)の実を身につけて、高い場所に登り(登高)、菊の酒(菊花酒)を味わい、厄除けをしました。
日本には、平安時代の初期に宮中行事として伝わり、菊を愛でる文化や、菊に綿をのせ露と香りを移す「着せ綿(きせわた/被綿)」の風習が広まりました。
江戸時代になると五節句の一つとして庶民の間にも浸透。
菊酒だけでなく、収穫祭の意味も込められ、栗ご飯を食べる習慣もあったようです。
五節句
五節句:人日(1/7)、上巳(3/3)、端午(5/5)、七夕(7/7)、重陽(9/9)
元々は中国から伝わった、奇数が重なる日に邪気を払う行事でしたが、日本で農耕の無事を願う行事と結びつき、江戸時代に公的な祝日と定められたことで、今の年中行事として定着しました。
| 節句 | 日付 | 別名 | 主な行事・意味 | 行事食・風習 |
|---|---|---|---|---|
| 人日の節句 (じんじつ) | 1月7日 | 七草の節句 | 一年の無病息災を願う | 七草がゆ |
| 上巳の節句 (じょうし) | 3月3日 | 桃の節句 ひな祭り | 女児の健やかな成長を祈願 | 菱餅・ひなあられ・白酒 |
| 端午の節句 (たんご) | 5月5日 | 菖蒲の節句 | 男児の健やかな成長を祈願 | 柏餅・ちまき 菖蒲湯 |
| 七夕の節句 (しちせき) | 7月7日 | 笹の節句 | 星に願いを託す、 裁縫・芸事の上達 | 素麺 短冊に願い事 |
| 重陽の節句 (ちょうよう) | 9月9日 | 菊の節句 | 長寿と健康を祈る | 栗ごはん・菊酒 着せ綿 |
何をする日?—“これだけ”実践リスト
菊の花を観賞する宴「観菊の宴」を開いたり、菊を用いた厄払いを行ったりすることで、無病息災や不老長寿を祈願します。
忙しくてもOK。今日からできる順に並べました。
1) 菊を飾る(菊=長寿の象徴)
- 小菊を数本、玄関・ダイニング・洗面台へ。
- 白・黄・ピンクなど、明るい色を低めの花器でまとめると品よく。
- 写真映え:花器の下に和紙 or 麻布を一枚敷くと雰囲気UP。
2) 菊のお酒/お茶を味わう
- 菊花酒(きっかしゅ):手に入らなければ、菊花茶(食用菊・乾燥菊)で代用可。
- ノンアル派は菊花+ジャスミンのブレンドティーもおすすめ。
3) 行事食を一品だけ

- 一部地域で「栗の節句」とも。栗ごはんが王道。
- 食用菊のおひたし、なすの煮浸しも相性◎(秋の実りで邪気払い)。
- 時短:レトルトの栗ごはんの素+新米で“旬の香り”を。
4) 「着せ綿(きせわた)」で清める(できる範囲で)
前夜〜朝に、菊の花に清潔な綿をそっとのせ、露と香りを移す。
翌朝、その綿で手や顔をぬぐう——長寿を願う古式ゆかしい所作です。
5) 観菊・登高(散歩でOK)
- 近所の高台・展望台・屋上庭園へ。夕方の風は秋の香り。
- 菊の展示会・神社の重陽祭をチェック(各地で開催)。
※福岡だと「筥崎宮放生会」でも、菊の展示があります。
6) 「後の雛(のちのひな)」を楽しむ
後の雛とは、桃の節句(雛祭り)で飾った雛人形を、半年後の重陽の節句で虫干しを兼ねて再び飾り、健康、長寿、厄除けなどを願う風習で、江戸時代に庶民の間に広がったといわれています。
- ひな人形を風通しして軽く飾る風習。厄除け・虫干しの意味合い。
- ミニ雛や写真で“リバイバル雛”でもOK。
よくある質問(FAQ)
- Q旧暦と新暦、どちらで祝う?
- A
日本では新暦9月9日が一般的。
ただし旧暦本来の季節感を重視して10月頃(旧暦9/9頃)に行事をする地域・施設もあります。
「お九日」は「おくんち」と呼ばれ、「博多おくんち」「唐津くんち」「長崎くんち」が行われます。
※北部九州では「おくんち」が行われます。
>>【博多おくんち2023】日本三大くんちって何?日程や見どころは?
- Q何を準備すればいい?
- A
小菊(または食用菊)、栗ごはんの材料、清潔な綿(着せ綿用)。
余裕があれば菊花茶や日本酒。
- Qお酒が苦手でも大丈夫?
- A
もちろん。菊花茶やジャスミンティー、ノンアル甘酒でOK。
- Q後の雛って必須?
- A
必須ではありません。虫干し・厄除けの意味で、無理なく楽しめば十分です。
Q5. 学校・職場でもできる?
- 机上に一輪挿し、休憩に菊花茶、菊の画像を壁紙にするなど、手軽に雰囲気を取り入れられます。
今日やることチェックリスト
- 小菊を買う or 庭の菊をいける
- 菊花茶/日本酒を用意
- 栗ごはんを炊く(レトルトでもOK)
- 前夜〜朝に着せ綿で清める
- 高台へ散歩(登高) or 菊の展示会へ
- ミニ雛で“後の雛”を楽しむ
むずかしい作法は不要。
菊・栗・着せ綿のいずれか一つでも取り入れれば、重陽の節句は十分に楽しめます。
重陽の節句まとめ
9月9日重陽の節句をご紹介しました。
日本の伝統行事は中国から伝わり、日本古来の風習と結びついて宮中行事となり、今日まで伝わっているパターンがけっこうあります。
重陽の節句はあまり馴染みがないかも知れませんが、菊酒を飲んで邪気祓い、栗ご飯で元気アップ!
・ブロガー:2021年9月ブログ開設
・趣味:旅行(国内・海外)、食べ歩き、写真撮影
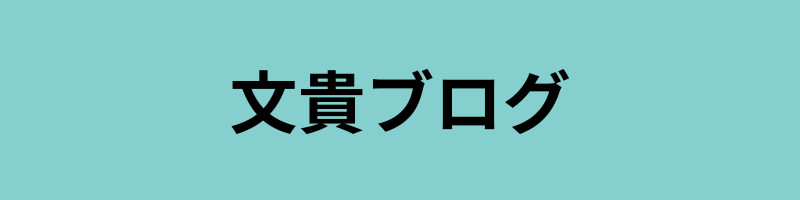













コメント