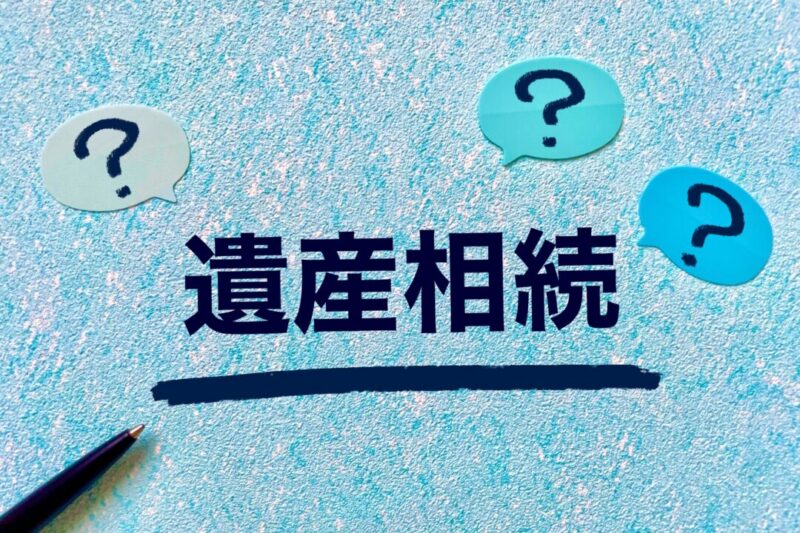
更新日:2025/10/01
「相続税の申告って、税理士に頼むといくらかかるの?」
そんな疑問を持つ方が年々増えています。
実際国税庁の統計によれば、2025年現在、相続税の申告件数は年間約15万件。
これは、もはや一部の富裕層だけでなく、一般家庭にも相続税申告が身近なものになっていることを意味します。
とはいえ、税理士に依頼するとなると「費用が高そう」「何にいくらかかるのか分からない」と不安になる方も多いはず。
そこで本記事では、2025年最新版の税理士費用の相場・内訳・注意点を徹底的に解説します。
申告ミスや期限遅れによるペナルティを避けるためにも、信頼できる税理士の選定と費用相場の把握は必須です。
「費用を抑えつつ、安心して申告したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
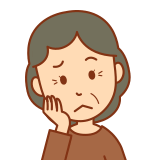
相続税の申告を税理士さんに頼むといくらぐらいかかるのかしら?

おおよその財産を把握して見積もりを取りましょう。
✅ この記事でわかること
- 相続税申告を税理士に依頼した場合の費用相場
- 費用の内訳と加算ポイント
- 安すぎる税理士に潜むリスク
- 見積もり時に確認すべき5つのポイント
🧾 はじめに:税理士費用は「見えにくいコスト」
遺産相続が発生すると、避けて通れないのが「相続税の申告」。
特に注意したいのが、配偶者の税額軽減を適用するには、必ず相続税の申告が必要だという点です。
「配偶者には税金がかからない」と誤解されがちですが、申告をしなければ軽減措置は受けられません。
結果として、本来ゼロだったはずの税金が課される可能性もあるのです。
しかし、いざ税理士に依頼しようとすると、費用の相場がわかりづらく、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
税理士費用の相場:遺産総額で変わる
2025年現在、相続税申告にかかる税理士報酬の目安は以下の通りです:
| 遺産総額 | 税理士報酬の目安 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 30万~60万円 |
| 5,000万円〜1億円未満 | 60万~100万円 |
| 1億円〜2億円未満 | 100万~250万円前後 |
| 2億円以上 | 300万円以上になることも |
報酬は「遺産の総額」「相続人の人数」「不動産の数・非上場株式の有無」などで変動します。
報酬体系は「定率制(遺産総額の0.5%〜1.0%)」や「基本報酬+加算報酬型」が主流です。
費用内訳
必要な手続き、おおよその費用の目安は、以下のとおり
○戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成:66,000円~
○相続財産調査:88,000円~
・預貯金残高・取引履歴の取得
・有価証券の残高評価
・不動産の登記情報、評価
○遺産分割協議書の作成:88,000円~
一番安いところだと1通1万円~
○預貯金の解約・名義変更:22,000円~
・有価証券(株式など)の名義変更
🧩 加算される可能性がある費用
税理士報酬には、以下のような追加費用が発生することがあります:
- 不動産評価費:1件あたり3万〜10万円
- 非上場株式の評価:10万円以上
- 遺産分割協議のサポート:5万円〜
- 二次相続のシミュレーション:数万円程度
- 特急対応(申告期限が迫っている場合):加算あり
⚠️ 安すぎる税理士に潜むリスク
「安いから」と税理士を選ぶと、以下のようなリスクがあります:
- 不動産評価が簡略化され、相続税が高くなる
- 節税特例(小規模宅地等の特例など)の適用漏れ
- 二次相続への配慮がない
- 税務調査対応が別料金
📋 見積もり時に確認すべき5つのポイント
1.報酬の計算根拠が明確か、業務範囲が具体的に記載されているか
「一式〇〇万円」ではなく、業務ごとの内訳を確認しましょう。
※後から追加費用が発生するケースもあります。
2.追加報酬の条件と金額が明示されているか
「基本報酬+加算報酬型」の税理士では、土地1筆追加ごとにいくら加算されるか条件を確認しましょう。
相続人は4人までは基本報酬内で、相続人が増える毎に追加報酬が発生する場合もあります。
3.相続税専門の税理士を選ぶ
法人税・所得税中心の税理士では、相続税特有の評価や節税策に弱いことも。
相続税申告の実績件数を確認しましょう。
4.税務調査対応費が含まれているか
遺産総額が増えるにつれて、後日税務調査が入る可能性が高くなります。
その際にアドバイスをもらえるかどうか、実際の現場に税理士が立ち会ってもらえるかどうか等、事前に確認しましょう。
5.実費(戸籍取得費など)の範囲が明確か
コンビニ交付サービスに対応している市町村ではすぐに取得できますが、対応していない市町村の場合は、郵送や現地に赴く必要があります。
※特に印鑑等証明書は、印鑑登録証持参で窓口で手続きするしかない市町村があります。
🧠 税理士費用は誰が負担する?
法的なルールはなく、相続人間での話し合いが基本です。
代表相続人が立て替え、後から精算するケースが多いです。
✅ 税理士費用を抑えるコツ
- 資料整理を自分で行う:通帳コピー、登記簿、保険証券などを事前に揃える
- 財産目録を自作する:Excelで簡易的に作成するだけでも報酬が下がる可能性あり
- 複数の税理士に見積もりを依頼:相見積もりで適正価格を把握
配偶者の税額軽減
✅ 制度の概要
- 対象者:亡くなった方の配偶者(婚姻関係にある者)
- 軽減内容:
相続した財産のうち、以下のいずれかまでの金額については相続税がかかりません。
・1億6,000万円
・法定相続分相当額
※上記のうち、多い方が適用されます。
⚠️ 申告しないと適用されない
ここが最も重要なポイントです。
配偶者の税額軽減は、相続税の申告をしなければ適用されません。
たとえ課税額がゼロになる場合でも、申告をしないと「軽減措置を使っていない」とみなされ、後日税務署から指摘を受ける可能性があります。
税理士費用まとめ:費用だけでなく「質」で選ぶ
相続税の申告を税理士に依頼した場合の費用の目安を紹介しました。
相続税申告は、一生に一度あるかないかの重大イベント。
単なる相続税申告書作成ではなく、財産を守るための専門業務です。
費用だけでなく、税理士の経験・対応力・節税提案力を重視して選びましょう。
もちろん自分で相続税の申告を行う事は十分可能です。
この記事を参考に、納得のいく選択をしてください。
但し、相続税の申告には期限がありますので、早め早めに行動しましょう。
・ブロガー:2021年ブログ開設
・フリーランス:2021年退職し、バリスタ(サイド)FIRE
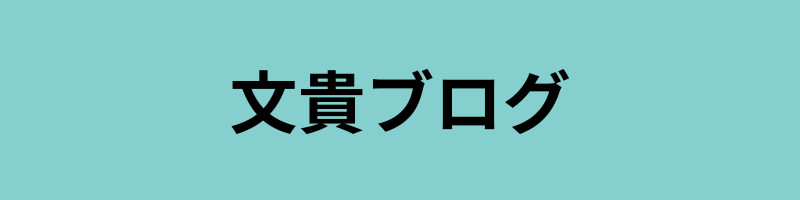



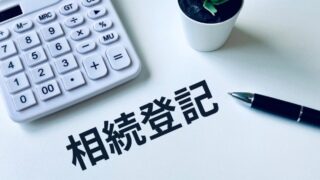

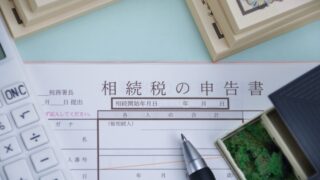
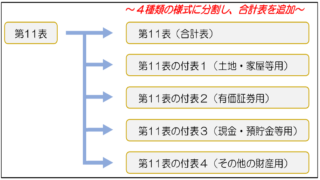

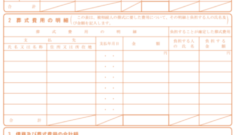

コメント